
つづいていくまちを紐解く
つづいていくまちは、地域ごとの文化が守られ、
その土地に生きる人たちが希望を持って生きていけるまち。
自然があり、心身の健康や学びがある。
やりたいことに挑戦できる環境があり、幸福がある。
私たちのようなローカルのインキュベーション施設は、
そんな「つづいていくまち」をつくるためにあるのではないだろうか?
「つづいていくまちを紐解く」では、さまざまな人の視点や取り組みを通して、
人の体温を感じられるような、
手ざわり感のある「つづいていくまち」を探っていきます。
「建築はまちの風景をつくっている」。
2022年4月にオープンした山形市の児童遊戯施設「シェルターインクルーシブプレイス コパル」(以下、コパル)をご存じでしょうか。コパルは「すべてが公園のような建築」をコンセプトに、障害の有無や国籍、家庭環境の違いに関わらず、すべての子どもたちに開かれた学びと遊びの空間として構想されました。オープン後は多くの来場者が訪れているだけでなく、2022年度グッドデザイン賞「グッドデザイン・ベスト100」や「2023年日本建築学会賞(作品)」など数々の受賞歴があり、建築作品としても注目されています。
蔵王連峰を背に田園風景の中に建つコパルは、山から降りてきた雲のような見慣れない形をしていますが、建物が描くやわらかい曲線は風景に寄り添い、見た目にも心地よさを感じます。そのコパルを設計したのが、建築家の大西麻貴さんと百田有希さんが共同主催する建築設計事務所「o+h」(オープラスエイチ)です。
建築というと、固くて、どこかひんやりしたものである、そんな印象を持っていました。ですがお二人が目指すのは、「愛される建築」や「道としての建築」だといいます。一度つくられた建築物は長く残り、まちの風景になります。それならば、愛されるものがいいじゃない。と、お二人が建築を語る際のあたたかい言葉に心惹かれ、ぜひ一緒に「つづいていくまち」について考えてみたいと思い、東京・日本橋にある事務所を訪ねました。
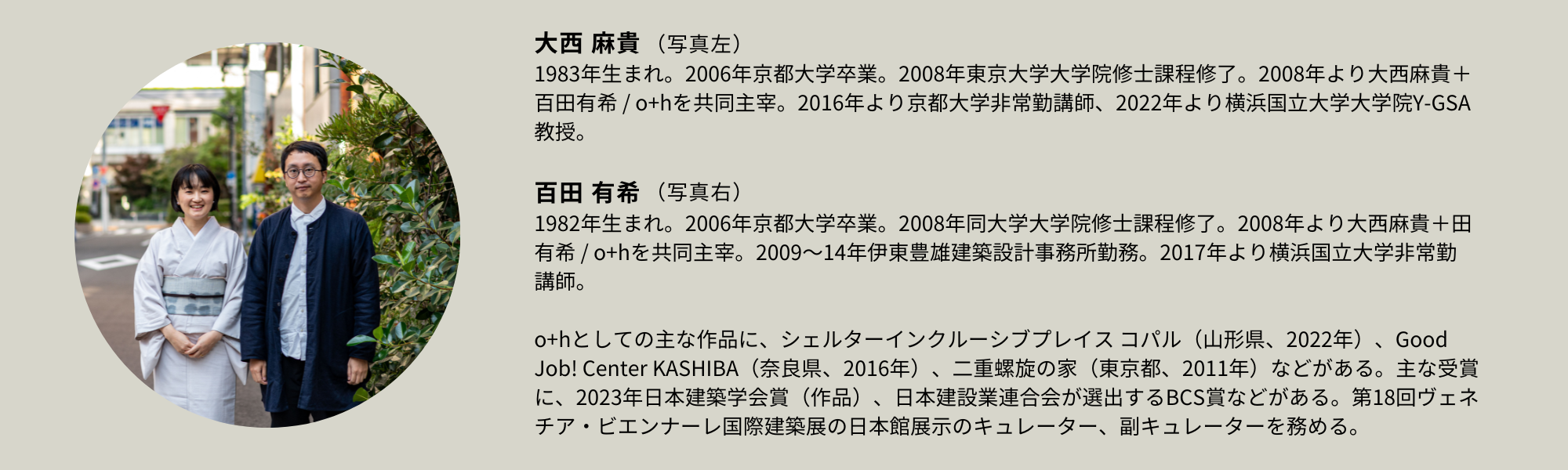
ーー私たちが森と暮らしのつながりを考えるときには、「いかに森との道をつくるか」がテーマの一つとしてあります。森に手を入れたり、資源をいただいたりするにも道が必要ですし、森と人の関係性をつなぎ直すにもメタファーとしての道が必要だと感じています。森と私たちの暮らしの間にあった道が現実としてもメタファーとしても途切れていると感じることが多々ありまして、「道」というものにとても興味があるんですが、お二人が建築を語る上でも「道」というキーワードが出てきたのを見て「道」について話したい!と思ってきました。お二人にとって「道」とはどういった意味合いなのでしょうか?
大西さん 道というのは、人間が自然に対して意志を持って通す最初の行為だと思っていて。私たちはそれがすごく建築的だなと捉えているんです。
ーー建築的、ですか?
百田さん 目の前に茂みが広がっている状態を思い浮かべるとわかりやすいと思うんですけど、そこを通ろうと思ったら、茂みを刈らないといけません。茂みを刈ると、そこに空間が生まれていきますよね。
大西さん そうすると、それまでは茂みだったものが、庭や屋根のように見えてくるかもしれません。「そこを通りたい」という誰かの意思が最初にあって、その後に多くの人の意思が連続していく。私たちが何かの建築に至るまでには、必ず何かしらの道を通ってアクセスすることがほとんどです。

大西さん そう考えるようになったのは、学生時代を京都で過ごしたのも影響しているかもしれません。京都は町家が並んでいて、通りと家の中の境界が曖昧な感じがします。都市計画もそうで、たとえば大徳寺へ行くときには、京都のまちを歩いて、お寺の境内へと入っていきます。それから高桐院の緑のトンネルのようなアプローチを抜けて、暗い部屋の中に入り、美しい庭に出会う……というように、建物そのものだけでなく、そこへ向かう経験全体が記憶として残っているはずです。建築を考えるときには、中と外を扉一枚で分けるよりも、道からつづく連続した経験の先に、私たちの建築がどのように位置付けられるかに興味があります。
ーーある場所に意図や意思が立ち現れる、それが人間的ということかなと思いました。自然の中で動物が歩きやすい場所を歩くとそこが獣道になるんですけど、彼らはただ茂みを横切っているわけではなくて。むしろ茂みを避けて通りやすい場所を歩くので、尾根沿いとかに道ができます。それに対して人間は、「この場所がこうなったら心地よくなるのではないか」とか、何かしらの意図を持って道を切り開くはずです。それはたしかに人間的だし、建築的なイメージがあります。
大西さん 「道」というキーワードが先にあったというよりは、自分たちがやりたい建築をやっていたら、気づいたら道みたいな建築ばかりだった、という順番なんですよね。京都の町家は、通りに出ても家の中とつながっているような感覚になるんですけど、そういう道のような空間が直感的に好きなのでしょうね。
百田さん 僕たちの事務所も元々はガレージだったんですけど、大掃除のときにはビルの中にある荷物が全部目の前の通りに出ます(笑)。

大西さん 講座をするときには外まで椅子を並べちゃったりして。昔からこの辺に住んでいた人に話を聞くと、かつては表具屋さんとかが通りで作業していたみたいで。通りは家の延長として使えるスペース、というイメージがこの辺りの地域にはまだあるのかもしれませんね。
ーー地域によっても違うと思いますが、商店街とか、場所によっては絶対にはみ出しちゃいけないシビアな場所もありますよね。でもそういう半分染み出す感じって重要ですよね。
大西さん ヨーロッパとかに行くと、カフェやいろいろなお店が道にはみ出していて、そういう光景はワクワクして楽しいですよね。
ーー以前、仕事でフィンランドへ行く機会があったのですが、日本と比べると、行政の施設にもこだわっている印象を受けました。見た目にも美しいですし、居心地がいいなって。日本だと公共建築にこだわっているイメージがあまりないというか、家具なども値段で決められることが多いですよね。でも、それによって失われていく地域の風景もあるんじゃないかなと思っているんです。
大西さん 「つづいていくまち」を考えたときに、建築もそうですし、“場”にできることはたくさんあると思います。社会のはじまりって、制度や法律からはじまると考える方もいるかもしれないし、経済行為からはじまると考える人もいるかもしれません。いろいろな方向から社会のはじまりを想像できると思うんですけど、自分たちの周りの社会を、“場”から出発して考えられないかなと私は思うんです。

大西さん まちがはじまるときに、そこにどんな場所があったらいいかを想像してみる。たとえば「少人数で集まって、まちの未来について本音で話せるような場所があったらいいな」とか。そのときに、場の雰囲気が排他的だったり、オフィスライクで冷たい印象のある空間だったりすると、心地よい会話は生まれにくそうですよね。そうやって、“場”から出発して自分たちのまちを考えてみることで、そこから発生する対話や活動の内容が変わってきたりする。どんな場所があるかということと、どんなまちが生まれてくるかというのは、実はつながってるのだと思います。
百田さん たとえば現在の福祉を考えてみると、障害者福祉や高齢者福祉や保育など、それぞれが別の建物で行われていますよね。僕らはそれが当たり前だと思っていますが、そのあり方が本当にいいと思ってそうなったのかは、ちょっと疑問に思っていて。まちの中に、「ここでみんなでご飯を食べたら最高だな」と思う場所があって、そこに高齢者の方とか子どもとか、障害のある人もない人もみんなで集まれる場所をつくろう、というように、場所を起点に考えると福祉のあり方も変わる可能性があると思うんです。

百田さん たぶんこれまでは、人口が増えていた社会の中で、なんとか福祉サービスを行き届かせようという視点から制度がつくられてきたのだと思います。でも、これからは人口がどんどん減っていくので、制度そのものを維持するのが難しくなっていくかもしれない。単にサービスの質を下げたりするのではなくて、小さくはなるんだけど、みんなが一緒にいられて、逆に豊かに感じられることだってあり得るんじゃないかなと思っているんです。場所から考えると、そういう転換も起こるんじゃないかなって。 僕たちは一つの建築をつくることを通して、建築を取り巻く環境や、その土地が持っている過去の記憶や歴史も含めた全体が生き生きと浮かび上がるような、そういうものをつくりたいと思っています。
ーーまちの機能と建築の話はとても興味深いですね。そうやって考えてみると、ヨーロッパでよく見る権威づけるような建物は階級制度と関連がありそうだなとか、いろいろと考えられそうです。だとしたら、これからのまちに必要な機能はどんなものなのか、あらためて問い直してみたいですね。
大西さん 私が社会人になってすぐに東日本大震災が起こったのですが、そのときに「東松島こどものみんなの家」という、約600世帯の方が暮らす仮設住宅の中にみんなが集まれるコミュニティの場をつくるプロジェクトに携わりました。
仮設住宅には、それまでいろいろな地域に暮らしていた知らない人同士が集まりますが、そこではある意味、ゼロから自分たちで社会を立ち上げていくようなところがあります。当時、同じ敷地内にある「ひまわり集会所」にみんなが集まって、住民が自分たちで自治会を立ち上げることになりました。集会所は毎日開けると決めて、集まってご飯を食べたり、餅つきをしたり、子どもが遊んでいたり。ごみの管理について、住民同士で話し合ったりされていたそうです。

大西さん あれから10年経ってみなさんとお話しする機会があったのですが、「社会は本来、あんな風にはじまっていくべきだと思った」と、仮設住宅に住んでいた方が言っていたのが印象的で……。自分たちのまちを、自分たちで立ち上げていく。そのときに必要なのは、インフラや制度が充実していることよりも、みんなが集まって困っていることを話し合えたり、気軽に行ける心の拠り所のような場所があることなのかもしれません。そんなことが思っている以上に大事だし、そこからはじまっていくことがたくさんあると感じました。
ーーいまはローカルでもコミュニティが残っている場所もあれば、なくなってきている場所もありますよね。その中で、支え合うまではいかないにしても、なんとなく顔が見える関係性がある方が、みんなにとっていい状態になりそうです。まちは変えられないものではなく、「つくり直せるもの」という考えを持つと、コミュニティとか、新しいカルチャーを創造していくことがすごく大事だなと思います。お二人が地域の風土や歴史も含めて、地域の人を巻き込みながら建築をつくっているというやり方そのものが、建物だけではなく、コミュニティをつくられているということなのでしょうね。
大西さん そうですね。私たちは公共建築とか、つくった建築がまちの財産になるようなプロジェクトに携わらせていただくことが多いのですが、いつもすごいなと思うのが、建築をつくるときにはみんながワクワクして、エネルギーが出てくるんです。新しくできる建物をきっかけに活動が生まれたり、それによってまちが変化していくという前向きな気持ちになる。建築にはスケジュールがあって、3年後とか、ちょっと先の未来に目標が設定されます。その目標があることで、「やろう」という気持ちが湧き上がってくるという、それ自体が建築の持つ一つの価値だなって。
今後は人口が減っていき、まちの中に新しい建築をつくること自体が少なくなっていくと思います。だからこそ、その時間を最大限に活かしたいなと思うんです。建築をきっかけに、もう一度まちのことを考えてみる。建築ができた瞬間から、みんなが自分の場所だと思って使いはじめられるような、そんな状況をつくれるといいなと思いながらプロセスを組み立てています。
ーーコパルの設計・施工期間中には、地域の方や行政の担当者の方だけでなく、設計や施工、運営に携わる方々が集まって話し合いの場を重ねたそうですね。たくさんの人が関わることによって起こる難しさもあるのではないかなと想像するんですが、どうやっていろいろな立場の意見を統合させていくんですか?
大西さん 私たちは具体的な建築に対するご意見を聞くこともありますが、 それよりも使い方について話すことがほとんどです。「ここに調理室があったら何をつくる?」とか。建築そのものより、その場所があったらやってみたいことを事前にやってみる、育ててみるようなことをしています。そうすると、「地域のお母さんたちのレシピをヒアリングしたいと思ってた」とアイデアが出てきたりして、一緒に山菜を採りに行ったり、イベントに発展していくこともあります。
百田さん 建築って、アプリのサービスとかに比べると単純なものだなと思うんです。極端にいえば、壁や柱をつくって、その上に屋根を乗せるということなので。そういうある種の図太さが、建築にはあると思うんです。だから要望もお聞きするんですけど、そもそも建築は全ての要望に対して、そんなに細やかに対応できるものでもないと思うのです。建築が持っている単純さが切り開くところもあるというか、居心地の良さとか、みんなが「わっ」と感動するとか、そういうことに力を注げるといいのかな。でも、使い手から話を聞くことによって、その場でどんなことが行われるのかを想像できるようになるので、それが重要だなと思っています。

大西さん たしかに、建築にはかなり荒々しいところはあるし、こういうプロダクト(手元にある湯呑み)を1個つくるときよりも、もっと粗い精度で見ている部分はあると思います。建築家にもいろんな考え方の人がいますが、それくらい荒々しくつくられた建築の方が風景の応答の仕方とか、風が流れていくとか、そういう建築ができる大きな骨格の部分がふさわしい形になっていると、細部まできめ細やかにつくられた建築よりもむしろ居心地がいい気がします。
ーーこれまでは、とくに公共施設のような大きな建物になると「心地よさ」はあまり重要視されてきていない気がしますね。後半では、ぜひその辺りのことからお聞きしていきたいと思います!
(聞き手・文・編集・取材写真:SEES NOTE 編集部)
▷後編はこちらからどうぞ!